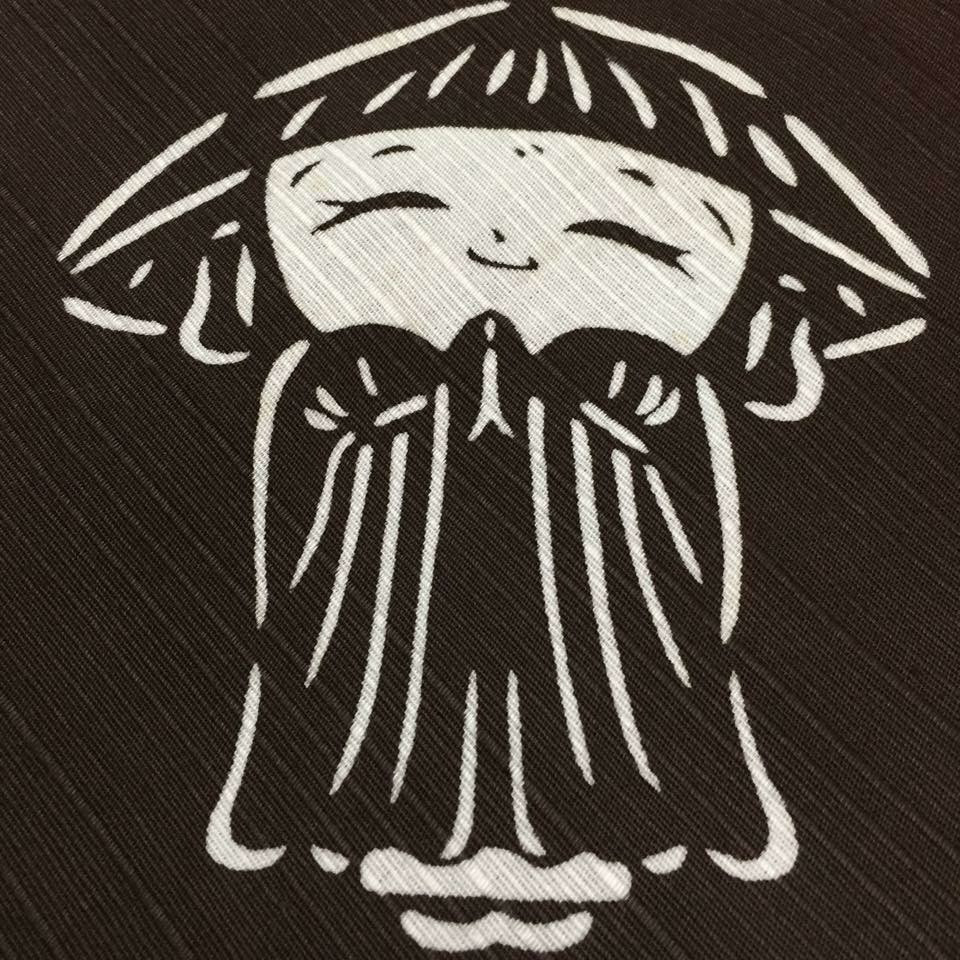ぷち豆知識
万灯会 精霊流し
地蔵盆
地蔵盆とは?
8月の23.24.25日を中心に行われる行事
地蔵信仰から生まれた行事です。
主に近畿地方で行われる行事で、関東から北ではあまり定着していない行事。
子どもの守り神とされる地蔵菩薩をお祀りすることで、子どもの幸せや健康を願う年中行事の一つとなっています。
地蔵盆にはお地蔵様にお供え物を捧げ、みんなでゲームをしたりお菓子を食べたりして楽しく過ごします。
旧暦7月24日以外の地蔵菩薩の縁日の24日は地蔵会(じぞうえ)、地蔵祭と呼ばれ、旧暦7月24日については盂蘭盆会(お盆)の時期に近く、それにちなんで地蔵盆やお盆祭の終りの日であったため地蔵盆と呼ばれるようになったという
お盆行事のラストイベントみたいなものですね。
喪中と忌中の違い
喪中ということは、自分にとって近しい方が亡くなっています。その際、宗派によって異なりますが、1年ほど喪に服します。
風鈴
風鈴の季節ですよね。
今日の雑学は風鈴
中国から伝わった「風鐸(ふうたく)」がもとになったと言われています。
古くは唐の時代の中国に、占風鐸(せんふうたく)という占いがありました。竹林の東西南北に、風鐸という青銅でできた鐘のようなものを吊るし、風の向きや音の鳴り方で物事の吉凶を占うもので、政治判断等が行われていたそうです。
この風鐸が、日本に仏教とともに伝わったと言われています。当時の日本では、強い風は流行り病や邪気などの災いを運んでくると考えられていました。風鐸は、その音が聞こえる範囲は聖域とされ、災いから守ってくれるものとしてお寺の軒の四隅に吊るされるようになったのだそう。当時は青銅製だったので、今の風鈴のような軽やかな音ではなく、やや鈍く重い音だったと言われています。
平安時代には、貴族が魔除けとして軒先に吊るしていたそうです。
風鈴の名は一説には法然さんが「ふうれい」と名付けたことに由来してます。
「風鈴」という表記は鎌倉末期に作られたとされる国宝『法然上人行状絵図』に「極楽の七重宝樹(しちじゅうほうじゅ)の風のひびきをこひ、八功徳池(はっくどくち)のなみのをとをおもひて、風鈴を愛して」とあり、これが後に「ふうりん」と読まれるようになったと言われてます。
江戸時代になると、西洋と貿易を行っていた長崎を通して、ガラスの文化が入ってきます。ガラスの風鈴もつくられました。かなり高額だったようです。
時は更に進みガラスの価格が徐々に下がり、庶民の手が届くようになると、住宅の縁側に吊るして楽しまれるようになりました。縁側は日当たりの良い南側にあることが多いのですが、南西が裏鬼門という不吉な方角にあたること、また気温が高い時期は伝染病が流行りやすかったことなどから、暑い夏に魔除けの意味も持って飾られたのではないかと想像されます。そのためか、この頃の風鈴といえば、魔除けの色である朱いものが主流だったそうです。
また、風鈴が流行る以前から、庶民の間では籠で鈴虫を飼って鳴き声を楽しむ習慣がありました。風鈴の音は鈴虫の声と似ているため、夏の終わりから秋にかけて鈴虫を飼うときには風鈴は仕舞われ、「風鈴は夏のもの」という風習が生まれたとも言われています。
最近では、魔除けの意味が薄れて、夏の暑さを凌ぐ季節のものになったようですね。
昨今は、コロナが猛威をふるい、世の中が不安定です。
風鈴の音色と共に、良い気を取り込んでみてはいかがですか?
#雑学 #風鈴 #魔除け #魔除 #風鐸 #夏の風物詩 #日本の文化 #japan #japanese #japaneseculture
夏の土用
20日から夏の土用ですね。
土用(どよう)とは?
土旺用事(どおうようじ)の略。
由来などは、過去に何度も説明してますので省略
一般的には立秋前の18日間の夏土用をさします。また、この期間を暑中と呼び、暑中見舞いを出す時期でもあります。
夏土用期間:7月20日~8月6日
最初の日を「土用入り」最後の日を「土用明け」といいます。
※上記の太陽黄径は入りの日のものです。
※入りの日によって18日間でない場合もあります。約18日間と解釈してください。
土用の丑の日
夏の土用は、1年の中で最も暑さが厳しいとされる時期にあたるため、江戸時代にはこの期間の丑の日を「土用の丑の日」と重視し、柿の葉などの薬草を入れたお風呂に入ったり(丑湯)、お灸をすえたり(土用灸)すると夏バテや病気回復などに効き目があるとされていました。
年によっては、土用の期間に丑の日が2回訪れることもあります。この2回目の丑の日を「二の丑」といいます。
2022年7月23日 、8月4日(二の丑)
うなぎ
7月の土用の丑の日にうなぎを食べると夏バテをしないといわれています。
実はこの風習、江戸時代の万能学者であり、発明家でもある平賀源内が仕掛けたものだったんです。
知り合いのうなぎ屋さんが夏はうなぎが売れないと困っていたのを見て、店の前に「土用丑の日、うなぎの日」という貼り紙をしたのです。
これが大当たりして、土用の丑の日にうなぎを食べる風習となりました。元々この日に「う」のつくものを食べると病気にならないという言い伝えがありましたので「う」のつく食べ物=「うなぎ」として定着したのでしょう。
栄養たっぷりのうなぎを食べて、夏バテを吹き飛ばしましょ。
土用の虫干し・土用干し
夏土用の時期に、カビや虫の害から守るため、衣類や書物に風を通して陰干することを土用の虫干しといいます。
また、この期間は田んぼに水を入れず、土をひび割れ状態にします。これは雑菌の繁殖を抑える効果があり、根がしっかりと張るんだそうです。
梅干しの天日干しもこの時期です。
土用にしてはいけないこと
・土を犯してはいけない(土を掘り起こしてはいけない)。
土用の期間は、土を司る土公神(どくしん・どくじん)という神様が支配するといわれ、土を動かしてはいけないとされてきました。今でも、家などを建築する際、土を掘り起こしたりする基礎工事などは土用の期間をはずす方が多いようです。
土用は季節の変わり目ですから、農作業で体調を崩さないようにとの戒めもあると思われます。
土用の間日(まび)
土用の期間中土を掘り起こしてはいけないとなると、いろいろと支障が出てきそうですね。でもご安心あれ。土公神が天上に行き、地上にいなくなる「間日(まび)」が設けられているので、この日は作業をしてもいいとされています。
夏土用の間日:卯・辰・申の日
※2022年は7月25日・26日・30日、8月6日
・土を掘り起こす作業をしない。
夏土用
・暑中見舞いを出す。
・衣類や書物の虫干しをする。
・梅干しの天日干しをする。
・薬草などを入れたお風呂に入る。
・うなぎや梅干しなど「う」のついたものを食べる。
うなぎ、梅干し、瓜、うどんなど「う」のついた食べ物
土用の丑の日のうなぎは有名ですが、昔からこの日に「う」のつくものを食べると病気にならないといわれてきました。
例えば「梅干し」「瓜」「うどん」など。いずれも、食が細くなる夏に食べやすいものですね。このような言い伝えは先人たちのありがたいアドバイスともいえるわけです。
全国には他にも「土用~」という食べ物があります。
土用餅 土用しじみ など
参考までに
#雑学 #土用 #土用の丑の日 #土用干し #土用丑の日 #土用の丑 #うなぎ #鰻 #ウナギ #間日