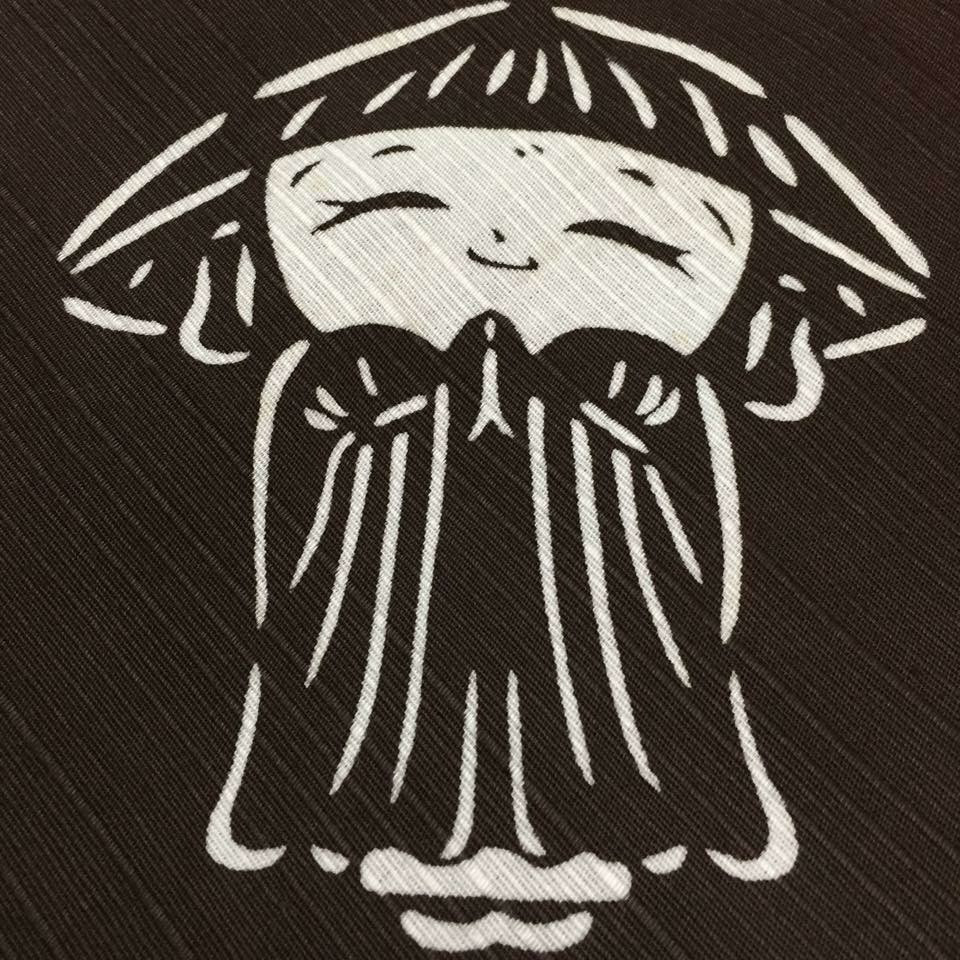ぷち豆知識
ハロウィン
もうすぐハロウィン👻🎃ですね
Halloweenの豆知識🎃
Halloweenとは
万聖節(キリスト教で毎年11月1日にあらゆる聖人を記念する祝日)の前夜祭。
秋の収穫を祝い、悪霊を追い出す祭りです。
語源・・・Hallow(神聖な)+een(even=evening)
万聖節はAll Hallow'sと言います。その前日である事からAll Hallow's Eveと呼ばれていたのが、Hallow E'enとなり、短縮されてHalloweenと呼ばれるようになったというのが 有名な話です。
起源
数千年前の古代ケルト民族の祭り(Samhain)が起源と言われています。
古代ケルト人の1年の終りは10月31日で、この夜は夏の終わりを意味し、冬の始まりでもあり、死者の霊が家族を訪ねてくると信じられていたが、時期を同じくして出てくる有害な精霊や魔女、悪霊が 横暴し、子どもたちをさらったり、作物や家畜に害をなす夜でもありました。死者の霊を導いたり、また悪霊を払いさったりする為、身を守るため仮面を被り、魔除けの焚き火を焚いていました。これに因み、31日の夜、カボチャ(アメリカ大陸の発見以前はカブが用いられ、スコットランドではカブの一種ルタバガを用いる)をくりぬいた中に蝋燭を立てて「ジャック・オー・ランタン(Jack-o'-lantern)」を作り、魔女やお化けに仮装した子供たちが近くの家を1軒ずつ訪ねては「トリック・オア・トリート(Trick or treat. 「お菓子をくれないと悪戯するよ」または「いたずらか、お菓子か」)」と唱えたのです。家庭では、カボチャの菓子を作り、子供たちはもらったお菓子を持ち寄り、ハロウィン・パーティーを開いたりします。お菓子がもらえなかった場合は報復の悪戯をしてもよいらしい。)
古代ケルト人と古代ローマ人がブリテン島を征服してから両民族の祭りが組み合わさっていきました。
起源は古く、古代ケルト民族のドルイド教の収穫祭の行事に、ローマの果家女神Pomonaの祭が加味されたものらしいです。 その後、キリスト教が伝来していき、現在のHalloweenという名前になったのです。
つまり、Halloweenは、古代ケルト・古代ローマ・キリスト教という3つの要素が混合したものなのです。
ラテン系国家では、宗教的色彩が強いが、イギリス・アイルランド・アメリカでは民族的習慣が教会的儀常時と並行して残存しています。
Trick or Treatの由来
仮装して子どもたちが練り歩き、窓をたたき"Trick or Treat"と言ってお菓子をねだるのは、祭り用の食料をもらって歩いた農民の様子を まねたもので、中世のなごりだそうです。
諸説あり😆
日本でいう「お盆」に近いのかな?
ご先祖様が家に帰るなど、どこかにてますよね。
重陽の節句
9月9日は、「重陽(ちょうよう)の節句」。
重陽の節句は、菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた菊酒を飲んだりして、不老長寿を願う行事の事
重陽の節句に欠かせないのが「菊」
旧暦では、菊の花が咲く季節であることから、「菊の節句」とも呼ばれてます。
古来中国の「菊水伝説」に由来し、
薬効の植物とされてきた菊が、平安時代に日本にも語り継がれ、不老長寿を願い邪気を払う花として定着。
重陽の節句では、菊酒を飲んだり、栗ご飯を食べる風習があります。
健康を願って、栗ご飯を食べて、菊酒🍶を呑んでみてわ
お施餓鬼
お盆にまつわるお話パート2
お施餓鬼といいますと、「ああ、あの暑いときの行事だな」とご存知の方も多いかと存じます。
前回お話したお盆(盂蘭盆会)とお施餓鬼は一対をなすものでして、今回はこれについてお話しましょう。
施餓鬼という字を分解してみると「餓鬼に施す」となります。なぜ「餓鬼に施す」ことがお盆と対をなしているといえるのでしょうか?
お盆の時期になると、ご先祖様たちはそれぞれの子孫の家を訪れます。これを出迎え供養するのが盂蘭盆会ですが、中には帰る家がない、あるいは帰れない者たちがおり、それらが餓鬼となります。
餓鬼とは、食べようとするものにはトゲが生え、飲もうとするものは火と変じてしまうという苦しみを持った存在です。
彼らを供養し慰め、食べ物をご馳走する法要、それがお施餓鬼の行事であり、それゆえ法要の際にあげるお塔婆では「無縁一切精霊」を供養することになっているわけです。
これがお盆と一対の行事であるといった理由です。
お施餓鬼の際、小さな旗をご覧になったり、持ち帰られたりした方がいるかと思います。
あれは「施餓鬼旗(せがきばた)」といい、昔は虫除けのお守りとして持ち帰り、畑に立てたものです。
畑の野菜が虫に食われるのは、餓鬼に食われたからだ、と考えていたからで、「うちはもう施したんだから、食べないでおくれよ」という意味があったのでしょう。
寺院の施餓鬼では「施餓鬼幡(せがきばん)」と呼ばれる旗を施餓鬼期間中に掲げます。この施餓鬼幡は宝勝如来・妙色身如来・甘露王如来・広博身如来・離怖畏如来の五如来の名前を記したもので、旗にその名前が記されます。盆棚に掲げられる旗もこの施餓鬼幡と同様のものが多いようです。
餓鬼はまたある種のご先祖様でもあります。きちんと施餓鬼供養されるとよいと思います。合掌🙏
マイYouTubeチャンネル
https://youtube.com/channel/UC-O8u5rdbdEy__LsHmffMPg
ホームページ
https://saimyouji.jp/
#仏教 #寺院 #仏閣 #寺 #temple #japanese #japan #japanesecarculture #寺院仏閣 #youtube #声 #お経 #北条時頼公ゆかりの寺 #北条 #鎌倉幕府 #真言宗 #最明寺 #山口県 #下関市 #菊川町 #japanesetemple #山口県十八不動三十六童子霊場 #霊場 #札所 #saimyouji #yutanisansaimyouji #お盆 #施餓鬼 #施餓鬼供養
お盆にまつわるお話
七夕の由来や飾り物