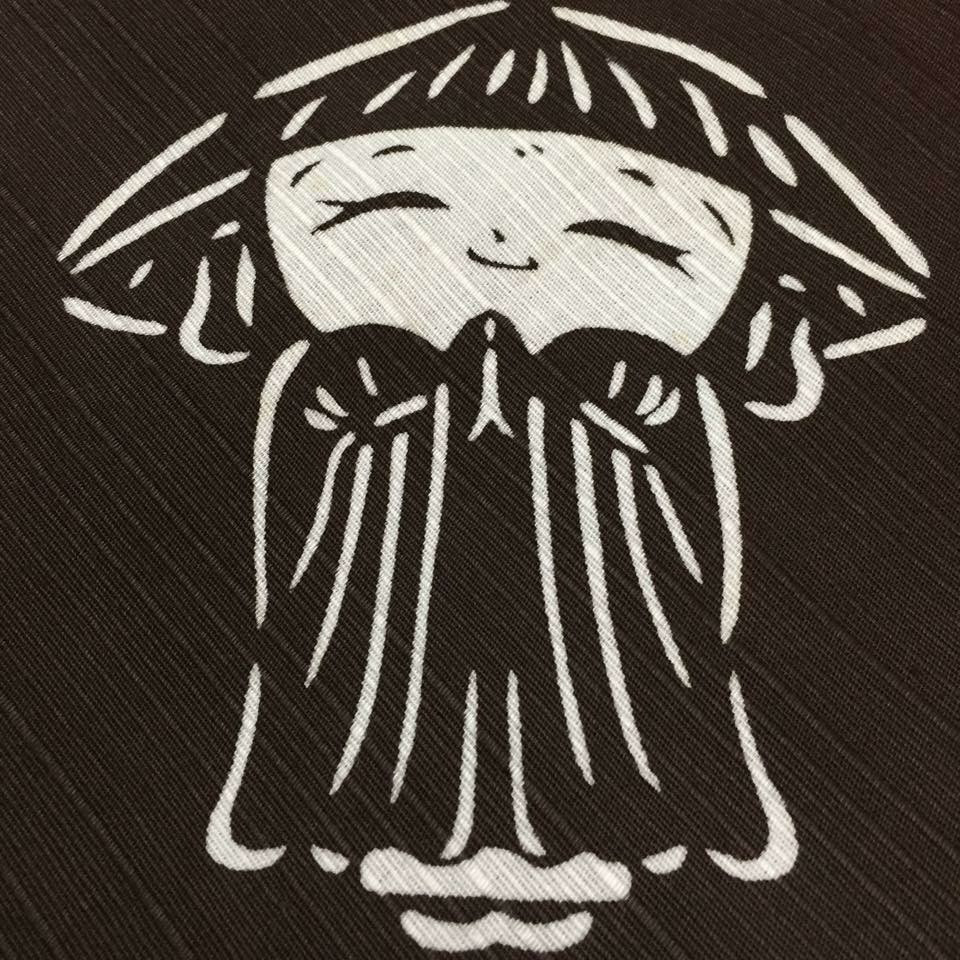ぷち豆知識
御影供とは?
真言宗の行事、今日明日は何の日?
明日4月21日は旧正御影供、高野山では今日は前夜にあたる御逮夜の行事が行われます。
旧正御影供とは、お大師様が奥之院にご入定なされました旧暦3月21日に、日頃からご加護を頂戴していることに感謝し、
お大師様に報恩の誠を捧げる法会です。
御影供
「みえく」広い意味では像の掛軸をかけて供養する法会(ほうえ)をいいます。
真言宗の宗祖弘法大師(空海)の御影を奉安してその報恩謝徳のために修する法会のこと。
毎月21日に修するのを単に御影供といい、弘法大師の御入定日(ごにゅうじょうび)である旧暦3月21日に
修するものをとくに正御影供(しょうみえく)と呼びます。
※行事日程は高野山のHPより
https://www.koyasan.or.jp/sp/kongobuji/event.html/kyusho/
御逮夜は荘厳な雰囲気があり、おすすめです。
#今日は何の日 #御逮夜 #正御影供 #弘法大師空海 #弘法大師 #高野山 #高野山真言宗 #japan #temple #伝統行事 #空海
百箇日とは?
百箇日とは?
100日法要とは、卒哭忌(そっこくき)とも呼ばれ
卒→終わる
哭→悲しみに大声で泣き暮れる
この様な意味があり、100日法要を区切りとして、
遺族が日常生活を送り始める区切りの日
(大切な人を失った悲しみや苦しみに別れを告げ、前に進むための大切な儀式)
また100日法要は、故人が閻魔さまから再審を受ける日を百箇日(ひゃっかにち)法要とも言い、
故人の魂がより良い救済を受けられるように、またその家のご先祖として祀られる最初の法要を、
遺族が供養を行うという意味があります。
新たなスタート、区切りの大切な法要
それが100日法要なのです。
皆様の祈り、大切な想い、感謝の気持ち
新たな生活がはじまりとなる日
初七日から四十九日まで
初七日から七七日までの意味
初七日から七七日まで、故人がどの世界に行けるか、閻魔さまの裁判を
受け、徳を積む修行を行ったり、故人がお世話になった方々へお礼参りに行ったりする期間。
また残された者(遺族や親族)が法要をつとめる事により、
この世からあの世へ徳を送ることができ、故人の徳が増し、より良い世界へ
選び導かれるとされてます。
法要の種類 時期(死後) どんな裁きを審査されるか
初七日 7日目 故人が三途の川を渡り、「泰広王(しんこうおう)」が生前の殺生について調べます。
二七日 14日目 「初江王(しょごうおう)」が生前の盗みについて調べます。
三七日 21日目 「宋帝王(そうたいおう)」が生前の不貞について調べます。
四七日 28日目 「五官王(ごかんおう)」が生前に嘘をついてないか調べます。
五七日 35日目 水晶の鏡に生前の罪状が写し出され「閻魔大王(閻魔大王)」が調べます。
六七日 42日目 「変成王(へんじょうおう)」が生まれ変わる条件を加えます。
七七日 49日目 「泰山王(たいせんおう)」が六つの世界の中から故人の行く先を選びます。
初七日から四十九日の法要を行う意味について
故人は、亡くなられた日を合わして49日の間、
後生(来世)を定めるための修行をされます。
その間に、7日毎に決まった仏様に7回逢われます。
その際に行うのが、初七日忌や二七日忌等であります。
総称して、お逮夜(たいや)法要といいます。
遺族にとっては、故人の冥福を祈り、喪に服する期間であり、忌中(きちゅう)
といいます。その期間を終えることを、忌明け(きあけ)といい、
四十九日の法要を営みます。
亡くなられた方が七日毎に逢われる仏様は下記の通りです
初七日忌(しょなぬかき)不動明王(ふどうみょうおう)
二七日忌(ふたなぬかき)釈迦如来(しゃかにょらい)
三七日忌(みなのかき) 文殊菩薩(もんじゅぼさつ)
四七日忌(よつなのかき) 普賢菩薩(ふげんぼさつ)
五七日忌(いつなのかき) 地蔵菩薩(じぞうぼさつ)
六七日忌(むなのかき) 弥勒菩薩(みろくぼさつ)
七七日忌(しちなのかき) 薬師如来(やくしにょらい)
【*四七日(よんひちにち)】
それぞれの仏様や仏様の前での故人についての説明
・不動明王(初七日)
恐ろしい形相で、右手には剣と左手には縄、背には火をまとい、
片目を閉じていらっしゃる仏様です。
恐ろしい形相は、人間の心にあるたくさんの煩悩や邪悪な心をいましめる為。
右手の剣は、煩悩や悪い人間関係を断ち切る為。
左手の縄は、邪悪な心や苦しめる悪いものを縛る為。
背中の火は、外敵や心の煩悩を焼き払う為。
開いた片目は一筋に迷うものを見つめ、閉じられた目には
母のような慈愛の涙がうかんでいます。
故人は、不動明王の前で過去の懺悔をされています。
釈迦如来(二七日)
紫がかった金色をしていて、三十二相・八十好種の特徴を備えておられます。
“三十二相・八十好種”とは、人相・手相・骨相や足相など三十二の気高い相と
八十の美しい特徴を持っておられることです。
全てのものに慈悲の心をかけ、どのような人の懺悔でも聞き入れ
改心させなければならない役目を持っておられます。
故人は、不動明王の前で懺悔したように、ここでも前世の行いを懺悔します。
文殊菩薩(三七日)
獅子に乗り、右手に剣を持ち、左手に経典を持っておられます。
右手の剣は、物事を正しく判断する知恵の力を与える為。
左手の経典は真理の聖典であり、萬物の仕組みや道理が記されております。
故人は、文殊菩薩さまには智慧を授かります。
普賢菩薩(四七日)
優しい顔立ちをし、白い象に乗っておられます。
白は清くけがれないことを表し、象は大きく柔らかい体をしていますが、
とても辛抱強く、いつも落ち着いています。
相対するものへ清く優しい慈悲の心を持ち、辛抱強くなるようにと願っておられます。
普賢菩薩さまは、施し・戒律・忍耐・精進・精神集中・智慧の獲得による修行で
悟られた仏様です。
故人には、修行で得たすべてのことを授けて下さります。
地蔵菩薩(五七日)
地蔵菩薩とは、私たちに大変馴染み深い“お地蔵様”のことです。
大地の蔵という意味の名で、五つの徳を持っておられます。
1.どのようなものでも平等に乗せる。
2.萬物を生み出す。
3.萬物を育てる。
4.じっと辛抱する。
5.すべてを包み込む。
大きな徳を持った地蔵菩薩さまは、病魔や苦しみを取り、徳を与えて下さります。
また、どのような所でも参られ、すべてのものを救われます。
故人は、地蔵菩薩さまに、苦しみを取ってもらい徳を授けていただきます。
弥勒菩薩(六七日)
弥勒菩薩さまは、慈愛の仏様です。
お釈迦様と堅い約束をされております。
お釈迦様が涅槃に入られて(涅槃に入る:お釈迦様が亡くなられること)、
五十六億七千万年後に、お釈迦様の代わりに、この世の人々の救済を誓われています。
故人は、弥勒菩薩さまに慈愛の心を授かります。
自分自身の悟りだけでなく、他のものの悟りへの手助けを教わります。
薬師如来(七七日・四十九日)
左手には薬壺を持ち、右手には印を組んでおられます。
薬壺からは、そのものに応じた薬を取り出し与えて下さります。
右手の印は、“施無畏の印”といい手の平を外に向け親指だけ折り曲げているものです。
これは、“あなたの不安な心や、恐怖心を取り除いてあげますよ”という印です。
故人は、これまで仏様の導きにより、懺悔し、知恵を授かり、苦しみを取って頂きました。
薬師如来さまには、後生が定まる前に最後の確認をくださいます。
ここで、まだ苦しみが残っている場合、それを取り除いて下さいます。
とても重要な四十九日間
ご葬儀後に、故人が仏様に七回逢われ修行を行っておられる49日間は、大変重要なものと考えております。
遺族の方の都合もありますが、7日毎の法事・法要での供養を行って頂くようお願いしております。
供養をするということは、善行を積むこととされており、それは功徳を積むと同じ意です。
功徳は、故人の魂を磨き、遺族の方たちの魂も磨きます。
ただ、世間体があり供養をするや、自分自身に返ってくるからというような気持ではなく、損得を超えたところで、心から故人への感謝の念を持ち、冥福を祈り喪に服すのが大事です。
どうぞ、その心を持って、ご供養いただければ幸いです。
春の土用4月17日〜5月4日まで
春の土用
春土用:4月17日~5月4日
土用期間にしては行けない事を
しても良い日を間日といい
春土用の間日:巳・午・酉の日
※2022年は4月22日・23日・26日、5月4日
春の土用は五月病になったり、やる気が無くなることに注意が必要といわれています。
春の土用は戌(いぬ)の日に「い」のつくものや白いものを食べるといいそうです。
「いわし」「いちご」「イカ」「いんげん豆」「芋」「大根」「しらす」など
2022年の土用戌の日は4月27日(水)です。
土用期間にしてはいけないこと
「土を犯してはいけない
(土を掘り起こしてはいけない)」
土を司る土公神(どくしん・どこうしん)という神様が支配するといわれ、
土を動かしてはいけないとされてきました。
してはいけないこと↓
☆土をいじること
・地鎮祭
・造園・土木・エクステリア工事
・土を動かすこと(盛り土・穴掘り含む)
・井戸掘り
・土いじり(ガーデニング含む)
・新居の購入
・増改築、リフォームを始めること
☆移動すること
・引越し
・吉方位旅行
☆新しく物事をスタートさせること
・開店・開業
・新規プロジェクトの着工
・新規の契約
・就職・転職
・結婚・結納
・新居の購入
土用にしてはダメな事が多い理由。
それは「土用期間はパワーダウン期間」だから!
その間は間日を活用しましょう!
葬儀にまつわる用語①
引導(いんどう)とは、
仏教用語です。
仏教の葬儀において、亡者を悟りの彼岸に導き済度するために、棺の前で導師が唱える教語(法語)、または教語を授ける行為を指します。
もとは、衆生を導き、仏道に引き入れ導くことという意味でありますが、そこから転じて前述の意味として使われるようなりました。
真言宗 - 引導法です。
導師が引導法の次第に基づいて、秘印明(印)を授け、灌頂を行います。
灌頂(かんじょう, 梵: abhiṣeka, abhiṣecana)とは、菩薩が仏になる時、その頭に諸仏が水を注ぎ、仏の位(くらい)に達したことを証明すること。
密教においては、頭頂に水を灌いで諸仏や曼荼羅と縁を結び、正しくは種々の戒律や資格を授けて正統な継承者とするための儀式のことをいいます。
日本密教の灌頂
•結縁灌頂(けちえん かんじょう)
出家や在家、あるいはその対象を問わず、どの仏に守り本尊となってもらうかを決める儀式。
投華得仏(とうけ とくぶつ)といい、目隠しをして曼荼羅の上に華(はな)を投げ、華の落ちた所の仏と縁を結ぶところから結縁灌頂の名があります。
各曼荼羅には鬼神や羅刹なども描かれますが、その場合でも、祀り方等や儀式を伝授されます。
•受明灌頂(じゅみょう かんじょう)
修行して密教を深く学ぼうとする人に対して行われます。
仏と縁を結ぶ入門的な結縁灌頂と違い、弟子としての資格を得る灌頂なので、弟子灌頂ともいいます。
また、密教を学ぶための資格である「十四根本堕」や、「八支粗罪戒」等の三昧耶戒を授かることから、現在の日本密教では「許可灌頂」(こか かんじょう)ともいいます。
•伝法灌頂(でんぼう かんじょう)
金胎両部伝法灌頂ともいいます。
阿闍梨という指導者の位を授ける灌頂。日本では、鎌倉時代に覚鑁の十八道次第を先駆とし成立した四度加行(しど けぎょう)という密教の修行を終えた人のみが受けられます。
ここで密教の奥義が伝授され、弟子を持つことを許されるのです。
また仏典だけに捉われず、口伝や仏意などを以って弟子を指導することができます。
伝法灌頂を受け阿闍梨位を得て、はじめて真言宗の正式な僧侶となるのです。
別名を「阿闍梨灌頂」、または「受職灌頂」ともいいます。
また、日本では鎌倉時代から幕末にかけて天皇の即位式には即位灌頂という行事が行われていました。
灌頂を受けた者として、後鳥羽院・後深草院の名が記録されています。